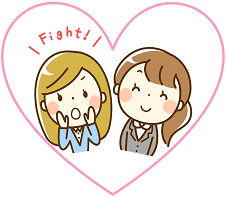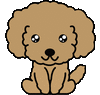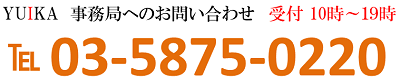Top / fc134
解体費用は建物種別と解体工事会社次第!【基本相場と安く抑える方法】
更新日2021-10-10 (日) 17:28:53 公開日2020年4月16日
家の解体費用の相場はいくらなの?
ここでは解体費用の相場や、解体工事業者の選び方、費用を安くする方法、補助金やローンの活用法などまで分かりやすく解説します。
★目 次★【解体費用の相場や、解体業者の選び方、費用を安くする方法、補助金やローンの活用法などまで分かりやすくを解説】

まず、家を解体するのはどんな時?
解体費用について考える前に、まず、どんな時に家を解体するのか考えてみましょう。
①家が老朽化してしまったので、建て替えるために解体する。
②所有している不動産(土地と家屋)を売却したいが、家が古いので取り壊して更地にした方が高く売れそう。
③相続した家が古くて誰も住んでいなく、維持管理が大変なので解体する。
④相続した家が古くて誰も住んでいないので、更地にして売却する(空き家の3000万円特別控除を利用するため)。
だいたい、このような場合に家を解体するのではないでしょうか。
不動産売買の実務に携わっていく中では、最近④の税金対策として家を解体してから売却するというケースが増えてきていると感じます。
まずは、空き家の3000万円特別控除について解説していきましょう。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
これは「空き家の発生を抑制するための特例措置」として、一定条件に該当する場合は譲渡所得(売却して利益が出た)に対して、3000万円までは、所得税・住民税が課税されないという税制優遇です。
この特例措置を利用するためには以下のような細かい条件が付されています。
適用要件
①適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期限である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡することが条件となります。
②相続した家屋の要件
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること(※)
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建物(マンション等の共同住宅)以外の建物であること
・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋(建物)を取得すること
※税制改正により2019年4月1日以降の譲渡については、下記2つの要件を満たした場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたものであると認められます。
⑴被相続人が介護保険等に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
⑵被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用、又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
⑶譲渡する際の要件
・譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること
・相続人が耐震リフォームをして売却すること。又は、相続人が家屋を取り壊して売却すること。
というような要件を満たす必要があります。
簡単にまとめると
「昭和56年5月31日以前に建てた家」を
「相続により取得」して
「耐震工事または建物を解体」して
「売却した場合」に、
譲渡益3000万円までは非課税となる制度です。
なお、被相続人(亡くなった方)の要件にも注意が必要です。被相続人は、亡くなる直前まで「相続する建物に住んでいた」もしくは「要介護認定を受けて老人ホームに入所していた」となっております。
「亡くなる直前に息子の介護を受ける為、息子の家に住んでいた」場合は、この特例措置は利用できません。
解体費用はどれくらいかかるの?(解体費用相場について)
解体する建物の構造が木造家屋なのか、鉄骨家屋なのか、鉄筋コンクリート造の家屋なのかによって、取り壊しにかかる手間や機材が変わってきます。その結果、解体費用は異なります。
建物構造・立地で変わる建物解体費用
一戸建てとマンションでは、木造家屋のほうが、鉄筋コンクリート造より解体しやすくなり使用する重機も違ってきます。
また、建物の立地条件によっても費用は変わってきます。

前面道路が狭くて重機が入っていけない、道路と高低差があり重機で解体ができない、そうなってくると、解体職人さんがえっちらおっちらとひたすら手作業で建物を解体しなくてはなりませんので、時間も手間もかかり解体費用は膨れ上がります。
実は、解体費用って都道府県によって相場も違います。
傾向として、都市部は取り壊し費用が高くなっています。
その理由は、田畑や空き地に囲まれた広々とした場所なら、周囲を気にせず重機などで簡単に取り壊しができますが、建物が隣接する都市部では近隣に注意しながら解体しなければならないからです。
あと、建物建材にアスベスト(石綿)が含有されているとこれまた解体費用は数十万円~加算されます。
また、解体する時期によっても違います。
解体業者は一般に12月から年度末の3月までが繁忙期となり、その他の時期とは坪単価が異なります。
この傾向は引越し業者と同じです。
ではおおよその解体費用を見ていきましょう。
解体費用は坪単価で計算する!
よく土地の価格を見るとき、「1坪いくら⁉」という表現をします。
実は解体費用も、この「坪」を目安に計算され、1坪いくらかで出しています。
「1坪」とは、㎡にすると約3.3㎡になります。
解体費用は 坪の価格×床面積 で計算されるのです。
マイホームで多い30坪の建物であれば、30坪×坪単価で出すわけです。
また、床面積は総床面積で計算します。
例えば2階建て以上の建物であれば、それぞれの階の面積を足した総坪数となります。
マイホームのように1階が15坪(50㎡)、2階が15坪(50㎡)であれば、床面積は30坪になります。
尚、坪単価のおおよその目安は下記の通りです。
木造家屋 4~5万円/坪
鉄骨造家屋 6~7万円/坪
鉄筋コンクリート造家屋 6~8万円/坪
が一つの目安となります。
坪単価の内訳は 解体費用+廃材処理費・整地費用です。
解体工事費用の中には、解体作業する人件費、付帯工事費用などが含まれます。
木造家屋で、仮に1坪約5万円とすると1㎡あたり1.5万円(解体費用1万円+廃材処理・整地費用5千円)が相場となるという事なのです。
もし30坪の木造家屋を取り壊す場合には、
木造家屋で120万円~150万円、鉄骨造家屋で180万円~210万円、鉄筋コンクリート造家屋で180万円~240万円となります。
その他の解体費用があがる要素としては、ブロック・フェンス・塀・駐車場部分のコンクリートの撤去、植栽伐根、浄化槽・井戸の撤去が必要な場合や地下室がある家屋の場合は別途費用が生じます。
解体費用が上がる可能性のある(別途計上の)費用とは?
解体工事には、以上「坪単価」に含まれない費用があります。
実は解体業者によって見積もり書の書き方は異なります。ここでは坪単価に含まれない主な費用項目についてのみご紹介します。
これらを計算していないと費用が思わず多額となり、思わぬ出費になるので注意するところなのです。
建物養生費…解体工事の現場を囲う養生シートの費用
一般的な2階建て住宅の養生費の相場は、10~15万円です。
重機回送費…解体工事で使用する重機運搬のための費用
重機を運搬する人の人件費やガソリン代です。
重機がリースだと、さらにそのレンタル料が発生する場合もあります。
だいたいの相場は、トラック1台につき3~5万円です。
近隣清掃費…近隣道路などを清掃する費用
だいたいの相場は数千~1万円程度です。
残置物処理…残置物とは居住していた人が建物や敷地内に残して置いていった私物です。
本棚やタンスなどの家具、冷蔵庫やテレビ、電子レンジなどの電化製品が当てはまります。また、自転車や物置、その他細かな生活用品なども残置物です。
実はこれらを処分する費用は近年とても高くなっています。
庭木の伐根…樹木の伐根作業は家屋の解体とは別作業なので、別途費用がかかります。
井戸の撤去…井戸が敷地内にある場合、この撤去費用もかかる場合が多々です。この費用だけで10万円前後もかかります。

~~~ 一昔前は木造で3万円/坪が相場と言われていましたが、建築リサイクル法による廃棄物ごとの分別処分が厳格となり、昨今は廃棄物の処分費用が高騰しているようです ~~~
解体業者の選び方
さて、解体費用の章でおおよその解体費用の相場をお伝えしましたが、解体業者によっても費用は変わってきます。
家を取り壊すのは一生のうちに何度もあることでは無いと思いますので、解体業者を選ぶのも何を基準に選択していいのか悩ましいところでしょう。
一番選んではいけないのは費用のみで選ぶ事です。
くれぐれも費用が安いからついつい選んでしまったとならず、「安かろう悪かろう」という言葉を思い出して取捨選択しましょう。
例えば費用が安いだけの業者を選んでしまうと、解体工事中の近隣トラブルや工事完了の仕上がり状態でトラブルが生じる可能性があります。
中には、解体工事で出る廃棄物を、適切に処分せずにどこかの山の中に不法投棄してしまうような、悪質な業者も存在します。
解体業者選びの3つのポイント
1.必ず現地で立ち会って見積もりをもらうこと
2.見積書は必ず書面でもらうこと
3.複数の業者から見積もりを取って比較すること
では、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
1.必ず現地で立ち会って見積もりをもらうこと
これは言うまでもありませんが、この業者は信頼できるのかどうか、誠意ももって対応してもらえるのかどうか、見積もりに来た担当者の対応によって見極めることが必要です。
2.見積書は必ず書面でもらうこと
解体業者によって提示してくる見積書のフォーマットはまちまちです。
「解体工事一式 150万円」という大雑把な見積書もあれば、「仮設工事・重機運搬費・内装解体・屋根解体・廃棄物処理費・樹木伐採・人件費」などの項目ごとの単価と数量をきっちり記載されている見積書もあります。
当然、後者の方が信頼できる業者といえます。
3.複数の業者から見積もりを取って比較すること
複数の業者から見積もりをとって、費用を比べるのも当然ですが、各社の担当者の対応も見比べましょう。
ここで解体業者には「解体を依頼するのは初めてで分からないことばかりなので、他の業者にも見積もりを依頼している」と伝えることが重要です。
どこの業者も相見積もりをとられることは嫌がりますが、「露骨に嫌な態度」をとったり、「他の業者の悪口」を言うような業者は断った方が良いです。
あと、建物を解体した後は法務局に建物滅失登記を行わなければなりませんが、その時に解体業者が発行する解体証明書や解体業者の印鑑証明書などが必要となります。
これらの書類について、こちらから質問しなくても丁寧に説明してくれる業者は良い業者と言えるかもしれません。
ちょっと一服
建築関係の業者と言っても役割によって色々な業者がいます。基礎工事業者・大工さん・内装屋さん・電気屋さん・外壁業者さん・外構工事屋さん、そして解体工事屋さんと。
この中で唯一「雨が降って喜ぶ」のが解体工事屋さんです。
解体工事中は粉塵が舞い散らないように水をまきながら建物を解体しますが、雨が降っていれば水を撒く手間が減るからです。
解体費用を抑える方法

1.業者を比較検討する
前章の通り、複数業者から見積もりを取って価格が安くかつ誠実そうな業者を選びましょう。
2.可能な限り自分で不要物を処分しよう
なんでもかんでも解体業者任せにしないで、自分で処分できるものは自分で処分しましょう。
特に相続で取得した家屋の場合は、家電や家具などがそのまま置いてあるということも少なくありません。
リサイクル業者などを利用して、お家の中を空の状態にしましょう。
3.情報を伝えよう
地中に埋設されている浄化槽や井戸、撤去してほしいブロック塀など、最初にきちんと伝えて後から追加費用が生じないようにしましょう。
4.自治体による助成金を活用しよう
空き家が増え続けているという社会的問題の背景には、少子高齢化、人口減少、住宅需要の都市部への移動などがあるようですが、実際に老朽化した空き家の解体を検討する際には、解体費用の捻出や固定資産税の負担増など、空き家の所有者が様々な問題に直面することが挙げられます。
まだ十分に普及しているとはえいませんが、全国約300の自治体に、空き家問題に対処するため、解体費用を賄うための補助金・助成金制度を設けているところもありますが、この助成金制度がまだ一般的にはあまり知られていないようです。
自治体によって名称や要件が違うようですが、多くても半分ほどの補助金が支給される自治体もあります。
下記に神奈川県愛甲郡愛川町の例を掲載しますが、必ず各自治体に問い合わせして、使える制度があるのか、適用要件を満たしているのかを確認しましょう。
行政機関の空き家解体費補助制度・一例(神奈川県愛甲郡愛川町の例)
神奈川県愛甲郡愛川町では、空き家の有効活用等を図るため、空き家バンクに登録された空き家を取得し、自ら居住するための住宅を建設する方に、解体費用の一部を補助しています。
なお、空き家解体費補助金は、その年度の交付額が予算の上限額に達すると補助金の交付ができなくなります。つきましては、申請の際には事前に環境課へお問合せしましょう。
補助対象者[次の要件をすべて満たす方]
空き家の所有者等から当該空き家を取得した方
空き家解体後に自らの居住の用に供する住宅を建設する予定の方
上記のほかにも、諸条件がありますので、詳しくはお尋ねください。
補助対象住宅
愛川町空き家バンクに登録された空き家
補助金の申請年度内に解体の完了が見込まれる空き家
施工業者を利用して解体する空き家
補助金額
施工業者を利用して解体した対象経費の2分の1以内(最大30万円)
なお、詳細は愛川町役場へお問い合わせください。
☛ 愛川町役場 空き家解体費補助制度
5.解体工事の時期と期間を考慮する
一般的には3月と12月が解体業者の忙しい時期と言われています。
この時期は必然的に解体費用も高くなります。
したがって、この時期を外せるのであれば外すのも一考です。
また、解体工事自体は着工から完了までおよそ10日もあれば完了しますが、解体期間が短いと解体業者も人数をかけなければなりません。
また解体業者はいくつも現場を受け持っているので、解体業者がスケジューリングしやすいように1カ月くらいの期間を提示しましょう。
「スケジュールは任せるから、急いでやらなくていいから解体費用をちょっと安くしてね」という意味です。
家の解体(取り壊し)の書類手続きについて
家を解体するに当たっては、さまざまな届け出や作業が必要になります。
どんな手続きや作業が必要なのか、ここで順序立ててひとつずつ見ていきましょう。
なお、この手続きや作業者は解体を依頼する解体業者が代行して請け負ってくれる場合がほとんどなので、まず解体を依頼するときに解体業者へ確認してみましょう。
電気・ガス・水道などのライフラインの停止
まず解体工事を行う前に、電気・ガス・水道・電話・ケーブルTVといったライフラインを停止しておかなければなりません。
手続きはライフライン業者によってさまざまで、電話のみで停止できるもの、届出書類を取り寄せて郵送しなければならないものがあります。
解体の直前になって申請すると、停止の処理が間に合わない場合もありますので、余裕を持って連絡して確実に止めましょう。
建設リサイクル法の申請
延べ床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、工事の1週間前までに建設リサイクル法の届け出をしておかなければなりません。
正式名称は「建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出」といい、工事現場の住所や工事内容などを記した書類を市区町村役場に提出します。
法律では施主が届け出をするようになっていますが、通常は解体主(建物所有者・建物名義人など)の委任状で、ほとんどの場合は解体業者が代理で行っています。
念のため、取り壊しを依頼する際に解体業者に確認しておいたほうがいいでしょう。
道路使用許可申請
解体に当たって、工事車両を道路に駐めて作業する場合には、道路使用許可の申請が必要になります。
申請書に駐車方法を記した図面を添えて、所轄の警察署に提出しなければなりません。
届け出には、数千円程度の証紙代がかかりますが、これもほとんどの場合、届け出は解体業者が行います。
近隣説明会などの開催
自治体によっては、解体工事前に近隣への説明会の開催が義務づけられているところがあります。
例えば東京都江東区では、工事開始7日前までに近隣住民へ説明会を開催して近隣の方への注意を促さなければなりません。
東京都江東区の場合
説明範囲
当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離(10メートルに満たない場合は10メートル)の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者
説明内容
解体建築物の規模及び構造
解体計画
(作業範囲、工期、解体方法、作業時間及び作業内容等)
騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
資材・廃材等の搬出経路及び工事車輌の通行経路
吹付けアスベスト等の有無及びその除去方法
東京都江東区では、事前に定められた標識を解体工事着手7日前までに区に提出し、解体工事着手の少なくとも14日(木造建築物の場合は7日)前から解体工事が完了する日まで設置しなけれないけません。
なお、どのような表示や説明が必要なのか、建物のある自治体の役所に確認してみるといいでしょう。この手続きも、ほとんどの場合は解体業者が代行してくれますが、念のために確認しておいたほうがトラブルも起こりにくくなります。
建物滅失登記
建物を解体したときには、法務局に届け出をして「建物滅失登記」を行わなければいけません。
たまにそこに既に無い建物で登記上まだ存在している場合を見受けたりしますが、建物を解体したらこの「建物滅失登記」をしておいた方がいいのです。
登記しておかないと固定資産税がかかってしまいます。
余分な税金を課税されないためにも、建物滅失登記を忘れないようにしましょう。
建物滅失登記自体には、登録免許税のような費用はかかりません。法務局の窓口で届け出方法を聞いて、自分で行う事もできます。
建物滅失登記は、解体工事完了から1カ月以内という期限が定められています。
その期限を過ぎてしまうと、10万円以下の罰金が科せられることがあるので注意しましょう。
解体業者が建物滅失登記まで代行してくれる事もあります。
代行を依頼する場合は、委任状や印鑑証明が必要になります。
また、司法書士や土地家屋調査士などに代行してもらう事も可能ですが、4万円程度の依頼費用がかかります。
解体にまつわる注意点
1.家を解体すると、固定資産税と都市計画税が高くる
固定資産税は1月1日に存在する不動産(土地・家屋)に課税されますが、住宅敷地(土地)は「住宅用地の特例」と呼ばれる軽減措置で、固定資産税や都市計画税が軽減されています。
ゆえに一見すると1月1日までに家を取り壊してしまったほうが、土地だけに課税されて固定資産税が安くなるような気がします。
しかし、住宅用地の特例として200㎡までを小規模宅地として固定資産税の課税標準額が1/6まで軽減されますので、家を解体してしまうと非住宅用地となり、軽減措置が受けられなくなり土地の固定資産税が3〜6倍に、都市計画税が1.5〜3倍になります。
もちろん建物が無くなるので、建物分の固定資産税と都市計画税は安くなるのですが、トータルでは納税額が3〜4倍になりますので、どちらが得かを計算してから解体の時期を検討しましょう。
なお2014年11月19日に可決された「空き家対策特別措置法」に伴い、行政が倒壊の恐れのある「特定空き家」とみなした場合には、建物が建っていたとしても、軽減措置が適用されないケースが増えていく事が想定されます。
2.地中になにか残っていない?
建物を取り壊して、更地にして売却しようとしている場合は地中の状態に注意を払いましょう。
土地売却後の売主の責任として一般的には引渡しから3カ月以内に「地中から廃棄物がでてきた」「土壌が汚染されていた」という事が発見された場合は、買主に対して保証しなければなりません。
よって、解体業者に解体を依頼する時は建物基礎部分の撤去の他に、80㎝~1mほど土をほじくってもらい、建築廃材やガラなどが地中に埋まっていないかを確認してもらいましょう。
また、一般の住宅が建っていた土地であれば問題はないと思いますが、店舗併用住宅でクリーニング業を営んでいた、ガソリンスタンドに隣接していた、といった場合は土壌が汚染されている可能性も否めません。
その場合は専門業者による土壌調査を行った方が良いでしょう。
3.隣地境界線上のブロック塀・フェンスはどうするの?
土地を売却する際に「今建っている古家は解体して更地にして引き渡しします」と買主と約束した場合、厳密にいうと敷地内にあるブロック塀やフェンスも取り除いた状態が「更地」となります。
しかし、お隣の家との境界線上に設置してある共有物のブロック塀などは勝手に取り壊す事はできません。
なので、更地にして買主に売り渡す場合はブロック塀やフェンスも撤去して引渡すのか、もしくは残るのかをしっかりと説明しておく必要があります。
また、高さが1.2mを超えるブロック塀は現行の建築基準法に抵触している可能性もありますので、もし残すのであれば「建物を建築する際に検査機関から指導されるかも」と伝えておく必要があります。
4.解体した方が良いの?
築40年経過している古家は建物を解体して更地にした方が売りやすいのか否か。
これは建物のコンディションによっては解体した方が良いかもしれませんし、中古戸建としてそのまま購入してリフォームして住む方がいるかもしれません。
どっちがいいか悩んだ場合は、中古物件として売り出してみて、購入する人がいなければ建物を解体して更地で売却することをお勧めいたします。解体しちゃったら元には戻せませんので。
5.解体しちゃっていいの?
ごく稀に、再建築ができない物件があります。そのほとんどが建築基準法で定める道路への接道義務を満たしていない物件です。
このような物件はリフォーム工事はできますが、再建築はできませんので、更地にしてしまった場合・・・・、困ったことになるでしょう。
私の家、ちょっと怪しいなと思ったら必ず近くの不動産会社に再建築できる土地なのかを聞いてみてください。
まとめ
ここでは解体費用の目安と、それを安く抑える方法について解説してきました。
家の解体は、そうそう経験する機会がないと思います。
不動産売却するなどのとき、更地にして売る場合、まずは、しっかりと仕事をしてくれる解体業者を選ぶ事が重要です。
解体費用が安いからと言って、くれぐれも「安かろう悪かろう」という業者を選んではいけません。
解体費用を抑える方法として相見積もりを取ることをお勧めしましたが、価格を競ってもらうのは二の次と考え、まずは業者の選別を行うために複数社に見積もりを依頼しましょう。
あなたの役に立ったらシェア!